-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年1月 日 月 火 水 木 金 土 « 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
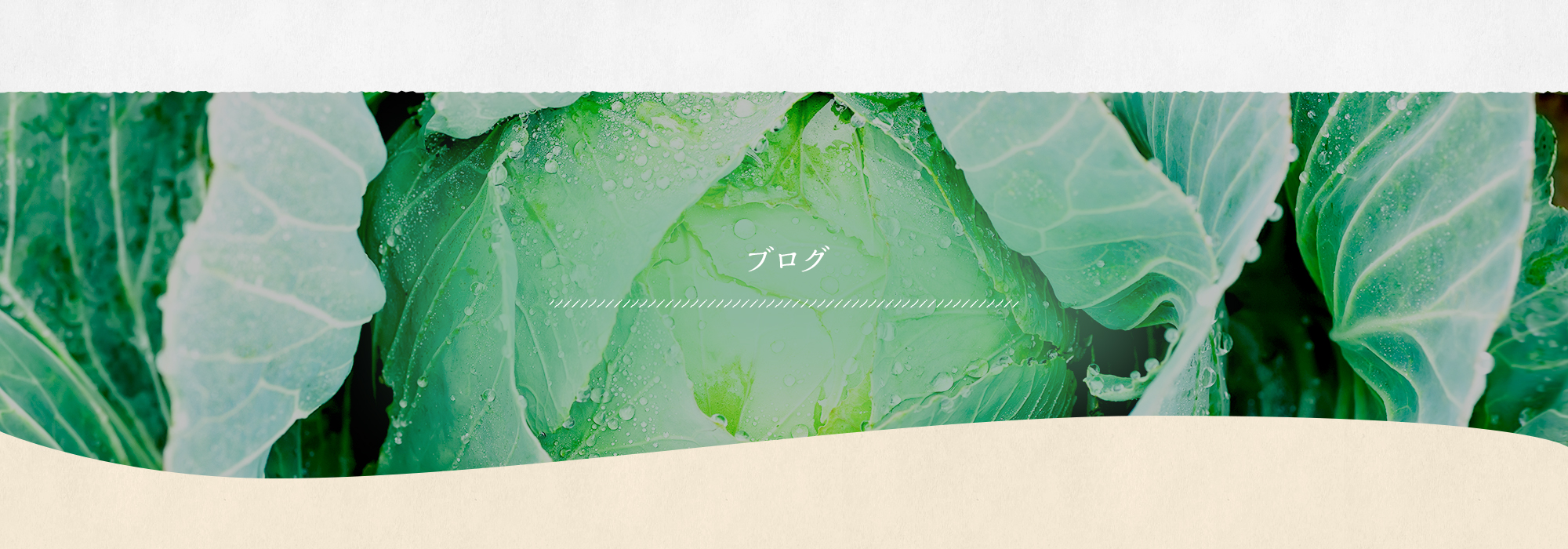
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
キャベツと聞いて、多くの方が思い浮かべる成分のひとつが
キャベジンではないでしょうか。
キャベジンとは、キャベツに含まれる
ビタミンUのことで、
胃腸の粘膜を守る働きがあることで知られています。
健康に良いイメージが強い成分ですが、
実は正しく知っておきたい注意点も存在します。
キャベジンは👇
胃の粘膜を保護する
胃酸の分泌を整える
胃の不快感を和らげる
といった働きがあるといわれ、
古くから健康成分として注目されてきました。
そのため👇
🍽 食生活が不規則な方
😣 胃の調子が気になる方
にとって、
心強い成分のひとつです。
キャベジンは万能成分ではありません。
摂取する際には、いくつかの注意点があります。
キャベジンは👇
🔥 熱に弱い
💧 水に溶けやすい
という性質があります。
長時間の加熱や、
茹でてお湯を捨ててしまう調理法では、
栄養が失われやすくなります。
👉 生食や短時間調理がおすすめです。
キャベジンは薬ではありません。
「キャベツを食べていれば胃の病気が治る」
という誤解を持つのは注意が必要です。
健康維持のためには👇
🥗 バランスの良い食事
🕒 規則正しい生活
が基本であり、
キャベジンはあくまで補助的な存在です。
キャベジンは、
必要以上に摂っても効果が増すわけではありません。
毎日の食事に👇
🥬 適量のキャベツを継続的に
取り入れることが、
最も現実的で健康的な方法です。
キャベツに含まれる成分を正しく理解し、
消費者に伝えることも、
農業・食品分野に関わる仕事の大切な役割です。
安全性
栄養価
正しい食べ方
これらを理解したうえで作物に向き合うことは、
信頼される生産者・担い手への第一歩です。
キャベジンは、
胃腸の健康を支える有用な成分ですが、
摂り方や理解を間違えると、その良さは活かせません。
正しい知識を持ち、
日々の食生活の中で無理なく取り入れることが大切です。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
〜キャベツがもたらす、胃にやさしい力〜
キャベツが「胃にいい」と言われるのは昔から知られています。
その秘密は、キャベツに含まれる成分「キャベジン(ビタミンU)」にあります。
このキャベジンこそ、自然が生み出した胃の粘膜を守る健康成分なのです。🌿
キャベジン(ビタミンU)は、キャベツから発見されたアミノ酸の一種です。
正式名称は「S-メチルメチオニンスルホニウム」。
胃の粘膜を修復し、荒れた胃をやさしく保護する作用があります。
そのため、昔から胃薬の成分としても利用されてきました。
キャベツを毎日食べることで、自然な形で胃の健康を保つことができます。
キャベジンは水溶性で熱に弱い特徴を持っています。
しかし、スープや煮物にすると、煮汁に溶け出した栄養を丸ごと摂れるため、
効率的に取り入れることができます。
ロールキャベツ・味噌汁・スープなどは、まさに理想的な調理法です。
寒玉キャベツの厚く丈夫な葉は煮崩れにくく、じっくり煮込む料理にぴったりです。
キャベツはキャベジン以外にも多くの栄養を持っています。
ビタミンC:免疫力を高め、風邪予防にも役立つ
ビタミンK:骨の健康を支える
食物繊維:腸内環境を整え、便通を改善
葉緑素(クロロフィル):抗酸化作用で体を守る
まさに、身体の内側から整える総合栄養野菜です。
冬の寒玉キャベツは、ゆっくりと育つ分だけ、栄養素がしっかりと蓄えられています。
キャベジンをはじめとするビタミン群も豊富で、胃にも体にもやさしい冬野菜。
寒い季節にこそ、キャベツスープや鍋に取り入れて、体を内側から温めてあげましょう。
キャベツ栽培や出荷の現場では、「食の安心・健康」を支える使命があります。
ただ育てて売るだけではなく、人の体調や生活を支える誇りがこの仕事にはあります。
「誰かの胃を癒やす」「家族の健康を守る」――
そんな気持ちで毎日畑に立つことができるのは、農業という仕事ならではの魅力です。🌾
キャベジンは、自然が生み出した“胃の守り手”。
そして寒玉キャベツは、そのキャベジンをもっともおいしく摂取できる冬の恵みです。
甘み、栄養、そして健康――。
冬の寒さが生み出すキャベツには、人の体と心を整える力があります。
寒玉キャベツを食卓に、そして生産現場に。
この一玉に込められた“自然と人の想い”を感じてください。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
〜冬の畑が生み出す、甘みと力の結晶〜
キャベツといえば、一年を通して食卓に並ぶ身近な野菜ですが、
その中でも冬に収穫される「寒玉キャベツ」は、ひと味もふた味も違います。❄️
寒さの中でじっくり育つことで、甘みと旨みを最大限に引き出す。
それが“寒玉キャベツ”の最大の特徴です。
寒玉キャベツは、晩秋から冬にかけての冷たい風と朝晩の霜を浴びながら、
ゆっくりゆっくりと時間をかけて育ちます。
寒さから身を守るため、キャベツは体内に糖分を蓄える性質を持っています。
だからこそ、冬のキャベツは甘くてみずみずしい。
生のまま食べても苦味が少なく、火を通すとさらに甘みが濃くなります。
ロールキャベツやスープ、味噌汁の具材としても最高の味わいです。🍲
寒玉キャベツは、春キャベツよりも葉が厚く、ぎっしりと巻いているのが特徴です。
切るときの「ザクッ」とした手応えは、まさに新鮮さの証。
加熱しても煮崩れしにくく、炒め物でもしっかりと存在感を保ちます。
お好み焼き・焼きそば・スープ・浅漬けなど、どんな料理にも万能に使えるのが魅力です。
美味しい寒玉キャベツを選ぶポイントは次の通りです。
手に持ったときにずっしり重いもの
外葉が濃い緑色でハリがあるもの
切り口が白くてみずみずしいもの
これらの条件を満たすキャベツは、畑でじっくり栄養をため込んで育った証拠です。
寒玉キャベツづくりは、冬の寒さと人の技の勝負です。
霜や雪の影響を受けすぎないよう、風よけネットや土壌の水はけ管理を行い、
自然の力と人の工夫を掛け合わせて育てます。
収穫のタイミングも重要で、早すぎると甘みが足りず、遅すぎると葉が固くなります。
気温・日照・湿度のバランスを見極める“職人の感覚”が求められるのです。
「農業=体力仕事」と思われがちですが、寒玉キャベツのような冬野菜の栽培は、
自然の変化を読む知恵と観察力が求められる仕事です。
寒さに耐えながらも、ゆっくりと力を蓄えて育つキャベツを見ていると、
まるで自分自身の成長を重ねて見守るような気持ちになります。🌅
畑で育てたキャベツが市場に出て、誰かの食卓で笑顔をつくる――。
その瞬間が、この仕事のいちばんのやりがいです。
寒玉キャベツは、冬の自然が生み出す“甘みの芸術品”。
寒さが厳しいほど甘くなるその性質は、まさに冬ならではの恵みです。
農業の現場では、この一玉に多くの手間と情熱が込められています。
自然と人が力を合わせた“冬の味覚”を、ぜひ味わってください。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
「寒玉キャベツ」は、冬の寒さに耐えながらじっくり育つキャベツの品種。
寒さにあたることで糖度が増し、生でも甘いのが特徴です。
その名の通り、“寒さの玉”と書く寒玉キャベツ。
外側の葉はしっかり厚く、中の葉はきめ細やかで柔らかい。
まるで自然が時間をかけて熟成させた“冬のごちそう”です。
寒玉キャベツの一番の魅力は、低温が作り出す糖の濃縮。
冬の畑では昼夜の温度差が大きく、
日中に光合成で作られた養分を夜間に溜め込むことで、葉の中の糖度が高まります。
霜が降りるころには、キャベツの内部がまるで果物のように甘くなり、
生で食べてもシャキシャキして柔らかい。
鍋や炒め物に入れると、熱でさらに甘みが引き立ちます。
外側の濃い緑の葉は、寒さから内側を守る“鎧”のような存在。
この厚みのおかげで、中心部は凍ることなく養分を蓄えることができます。
そして中の白い部分は、甘みが凝縮された“芯”のような味わい。
おすすめの食べ方
千切りサラダで甘みをストレートに味わう
ロールキャベツで煮込んでも型崩れしにくい
鍋料理でスープに自然の甘さをプラス
寒玉キャベツは、葉の巻きがしっかりしていて重みのあるものが良品です。
持ったときに“ずっしり”とした感触があれば、それは中までぎゅっと詰まっている証拠。
外葉が鮮やかな緑で、切り口が白く乾いていないものを選びましょう。
農家では出荷前に糖度計でチェックを行い、
納得できる甘みが出たものだけを市場へ送り出します。
その厳しい基準が、寒玉キャベツのブランド力を支えているのです。
寒玉キャベツは、生育に時間がかかる分、畑の管理が非常に重要です。
水の与えすぎは根腐れの原因となり、
逆に乾燥しすぎると葉が固くなる。
農家は天候を見極め、1日ごとに潅水や施肥を調整します。
また、冬の風に耐えるための根張りの強い苗選びもポイント。
強い苗ほど寒さに負けず、締まりのある玉に育ちます。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 甘み | 低温で糖度が上がる |
| 食感 | しっかりしていて柔らかい |
| 保存性 | 外葉が強く日持ちが良い |
| 料理適性 | 生でも加熱でもおいしい |
ひとことで言えば…
寒玉キャベツは、冬の大地がじっくり育てた“甘みの宝石”。
手間と寒さを乗り越えて育つその姿こそ、農家の誇りです。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
朝日が昇る頃、畑一面に広がるのは、まるで緑の波のようなキャベツの葉。
風が吹くたびに、葉の裏がきらりと光り、畑全体がゆっくりと揺れ動きます。
その景色はまさに“生命のうねり”。
農家の人にとって、この風景は単なる「作業場」ではなく、
何ヶ月も心血を注いできた努力の結晶です。
一つひとつの苗を植え、気候を見極め、水と肥料のバランスを取りながら育ててきた結果、
ようやくこの壮大な畑が完成します。
春の柔らかな緑、夏の力強い深緑、秋の黄金色の畑。
キャベツの畑は季節ごとに表情を変え、見る人を楽しませます。
特に寒玉キャベツのシーズンは、冬の澄んだ空気の中にピンと立つ葉が美しく、
霜が降りる朝はキラキラと輝いて、まるで自然のイルミネーションのよう。
冷たい空気の中で葉が締まり、甘みが増していくのがわかります。
広大な畑では、トラクターや移植機、収穫機が活躍します。
朝からエンジン音が響き、土の香りと混じり合う。
農業は“機械化”が進んだとはいえ、最後の判断を下すのはやはり人の目と手。
天候や土の状態を見極め、微妙な調整をするのがプロの仕事です。
農家の暮らしは、天候に左右される厳しい世界です。
雨が少なければ水を運び、風が強ければ苗を守る。
それでも、青空の下で風を感じながら働く時間は格別。
自然のリズムの中に身を置くことで、
人もまた「大地の一部」として生きている実感を得られます。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 風 | 生育のリズムを刻む自然の息吹 |
| 太陽 | 命を育てるエネルギー |
| 土 | 栄養を蓄える母なる大地 |
| 人 | それらを繋ぎ、育てる存在 |
💬ひとことで言えば…
広大な畑は、自然と人が共に作り上げた“生きたキャンバス”。
その景色の中に、農業の本当の美しさがあります。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
農業は「食材を生産する仕事」であると同時に、「消費者の健康と命を守る責任」を負った産業です。
安全な農薬の使用と管理
環境に配慮した持続可能な栽培
安心して食べられる品質管理
農家は消費者の信頼を背に、毎年挑戦を繰り返しながら作物を育てています。
数あるキャベツの中で、冬に旬を迎えるのが「寒玉キャベツ」。
葉が硬く詰まっていてずっしり重い
冬の寒さが糖度を増し、自然な甘みを引き出す
保存性に優れ、冬の間も新鮮な状態を保ちやすい
その力強い甘みは、まさに冬の食卓に欠かせない主役です。
ロールキャベツ:煮込むほど柔らかくなり、旨味を閉じ込める
鍋料理:豚肉や鶏肉と合わせてスープに甘みが広がる
炒め物:シャキッとした食感が残り、旬の味わいを堪能
寒さが育む甘みと歯ごたえは、他の季節のキャベツでは味わえない格別なものです。
寒玉キャベツは冬の厳しい環境下で育ちます。そのため農家は、
土壌改良や肥料管理で安定した成長を支える
冬場の冷え込みや霜害への対策を工夫
収穫期を見極めるために日々観察を続ける
一玉一玉に込められた農家の努力と技術が、冬の食卓を支えているのです。
スーパーで見かけるキャベツ一玉。
その裏には農家の労力と責任が詰まっています。
「このキャベツをどう料理しようかな」と思うとき、少しだけその背景を思い浮かべることで、食材への感謝や愛着が深まるはずです。
農業は「命を預かる責任」を担った仕事
寒玉キャベツは冬の甘みと栄養を凝縮した逸品
農家の努力が消費者の安心と健康を支えている
👉 冬のキャベツ料理を楽しむとき、その一皿には 農業の責任と誇り が込められているのです。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
私たちが一日の始まりに食べる朝食、家族と囲む夕食。
その食卓を彩る野菜や米、果物は、すべて農業の成果です。
普段は意識しないかもしれませんが、農家の努力がなければ、当たり前のように食材が並ぶことはありません。
農業は単なる生産活動ではなく、「命を育み、家庭の暮らしを支える基盤」 といえます。
食卓に並ぶ一皿の裏には、目に見えない工程が積み重なっています。
土づくり:有機肥料を混ぜたり、土壌分析を行い健康な畑を準備
種まき・苗植え:気候や地域に合わせたタイミングを見極める
栽培管理:水の管理、害虫防除、肥料調整など日々の観察
収穫:一番美味しい瞬間を見極めて刈り取る
出荷・流通:選別・梱包を経て市場やスーパーへ
消費者が手にする頃には、すでに何ヶ月もの時間と労力が費やされているのです。
新鮮な野菜は味わいだけでなく、家事や暮らしの質に直結します。
キャベツやレタスのサラダは「あと一品」をすぐに作れる便利さ
冬野菜を使った煮込み料理は、体を温めるだけでなく家族団らんの時間を豊かにする
彩り豊かな副菜は、食卓の見た目を華やかにし、食欲を増進
農業は「日々の健康づくり」だけでなく、「家族の心のゆとり」をも支えているのです。
農業から生まれる食材は、子どもから高齢者まで、家族全員の生活に役立っています。
子どもには成長に必要なビタミンや食物繊維を
大人には疲労回復や生活習慣病予防を
高齢者には消化しやすく体に優しい栄養を
「旬の食材を食べること」は、家族みんなの健康を守る自然な方法なのです。
農業は単なる「食材の供給」だけでなく、地域文化の継承にも深く関わっています。
冬のキャベツ鍋、春の山菜料理、夏の冷やし野菜、秋のきのこ汁…。
これらはその土地の農業があって初めて成立する食文化です。
農業を守ることは、その地域の歴史や伝統を未来へつなぐことでもあります。
食卓に並ぶ食材は農業の長い努力の結晶
野菜は健康だけでなく、暮らしの質を豊かにする
農業は地域文化や家族の絆を支える存在
👉 「いただきます」の一言の裏に、農業の存在が息づいているのです。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
~甘みと巻きの美しさを届ける~ ✨
寒玉キャベツは、春に種をまき、夏から秋に収穫される品種。
冷涼な高原で栽培されることから「高原キャベツ」とも呼ばれています。
この環境が生む寒玉キャベツは、ぎゅっと締まった葉と、噛んだときに感じる強い甘みが魅力。
普通のキャベツと比べて煮込み料理に向いているのも特徴です。
寒玉キャベツの大きな特徴は、その美しい巻き。
葉が何層にも重なり、まるで芸術作品のように整った形になります。
しかも加熱すると甘みがさらに引き立ち、スープや煮物にすれば旨みが溶け出して料理全体を引き立ててくれます。
ロールキャベツやポトフには欠かせない存在です。
ミウラ農場ではキャベツを大量に育てるだけではなく、一玉一玉を丁寧に管理しています。
葉の巻き具合や色合い、硬さなどを日々観察し、最適なタイミングで収穫。
「今日が一番美味しい」という瞬間を逃さないよう、スタッフ全員が責任を持って畑と向き合っています。
消費者に直接届くからこそ、農薬の使用は必要最低限に抑え、自然に寄り添った栽培を行っています。
「安心して食べてもらいたい」という思いがあるからこそ、見えない部分にもこだわりを徹底しています。
キャベツを口にしたときに「甘い!」「美味しい!」と笑顔になってもらうこと
――それが私たちの最大の喜びです。
その笑顔のために、寒玉キャベツづくりには日々の努力と工夫が込められています。
寒玉キャベツには胃に優しい「キャベジン」が含まれています。
この成分は胃潰瘍や胸やけを防ぐ働きがあり、古くから「胃の薬」としても重宝されてきました。
キャベツの甘みと健康効果は、まさに自然からの贈り物です。
寒玉キャベツは、自然環境と人の情熱が合わさって生まれる“作品”のような野菜です。
美しい巻きと強い甘み、そして安心して食べられる安全性
――これらすべてにこだわることで、全国の食卓に「笑顔」と「健康」を届けています。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培している
ミウラ農場、更新担当の富山です。
目次
~岩手の大地が育む野菜~ 🌱🍃
株式会社ミウラ農場がある岩手郡岩手町は、冷涼な気候と肥沃な土地に恵まれた農業の町です。
標高が比較的高いため、昼夜の寒暖差が大きく、作物にとって理想的な環境が整っています。
寒暖差があると、昼間に光合成で作られた糖分が夜に逃げずにしっかりと蓄えられるため、野菜の甘みが増すのです。
これはリンゴやブドウなど果物にも共通する「美味しさの秘密」🍎🍇。
キャベツも同じく、この自然のサイクルでぐっと旨みが引き出されます。
ミウラ農場の畑は、なんと東京ドーム17個分にも匹敵する広さを誇ります。
目の前に広がるキャベツ畑は壮観で、四季折々の景色が楽しめます。
春 🌸 …雪解けとともに畑が息を吹き返し、苗の植え付けが始まる。
夏 🌞 …キャベツの葉が青々と茂り、力強く育つ。
秋 🍂 …収穫のシーズン。畑はキャベツの緑で埋め尽くされる。
冬 ❄️ …一面が雪に覆われ、自然の休息時間となる。
自然の変化を体いっぱいに感じながら働けることは、農業の醍醐味でもあります。
「良い野菜は良い土から」――これは農家にとって普遍の真理です。
ミウラ農場では堆肥や有機質を用いて土を育て、フカフカで栄養豊富な土壌を維持しています。
キャベツは根をしっかり張ることで大きく美味しく育ちます。
根が深くまで伸びやすい柔らかな土をつくることが、丈夫で甘みのあるキャベツづくりの第一歩なのです。
岩手の大自然がもたらす澄んだ水と新鮮な空気は、野菜にとって大きな財産です。
雪解け水や山から流れる清流はミネラルを含み、作物に命を吹き込みます。
また、都会に比べて空気が澄んでいるため、病害虫の発生も少なく、健康的な栽培が可能です。
人にも野菜にも優しい環境といえるでしょう。
広大な自然の中で野菜を育てることは、自然に学び、自然に生かされる営みです。
天候に左右される厳しさもありますが、それ以上に「自然と共に生きる」豊かさがあります。
ミウラ農場では、地域の人々とのつながりも大切にしながら、自然と調和する農業を続けています。
冷涼な気候、肥沃な大地、清らかな水と空気――岩手町の自然環境は寒玉キャベツを育てる最高の舞台です。
この環境があるからこそ、甘みと旨みが詰まったキャベツが育ち、全国の食卓を支えているのです。
次回もお楽しみに!
ミウラ農場では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
岩手県岩手郡を拠点に冬玉キャベツを栽培しております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()